足首のアライメントとは?— 身体全体を支える“土台”のバランス

1. 足首の構造と役割
足関節(ankle joint)は以下の骨で構成され、これらが作る関節を距腿関節(きょたいかんせつ)と呼びます。
- 脛骨(けいこつ / tibia)
- 腓骨(ひこつ / fibula)
- 距骨(きょこつ / talus)
距腿関節は、背屈(つま先を上げる)と底屈(つま先を下げる)の動きを担い、歩行・姿勢維持に重要な役割を果たします。
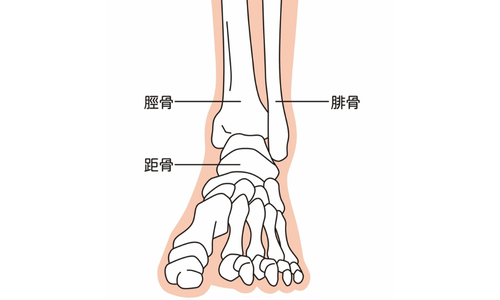
2. アライメントを観察する3つの視点
| 観察面 | チェックポイント | 主な異常例 |
|---|---|---|
| 前額面(正面) | 脛骨と踵骨が一直線か | 内反(踵が内側)/外反(踵が外側) |
| 矢状面(横から) | 背屈・底屈の可動域や重心バランス | 過剰な底屈=前足荷重/過剰な背屈=踵荷重 |
| 横断面(上から) | 足の回旋(内旋・外旋) | トゥイン(内向き)/トゥアウト(外向き) |
小さな歪みでも軽視は禁物。足首の「数ミリの傾き」が、膝や腰、首肩へのストレスにつながることがあります。
3. 全身への影響
足首のアライメント不良は、下肢から体幹へと「運動連鎖」を引き起こします。
- 過回内 → 膝の内反 → 骨盤前傾 → 腰痛
- 過回外 → 下腿外旋 → 股関節外旋 → 殿部やふくらはぎの張り
4. 臨床・スポーツ現場での対策
- 評価:距腿関節の可動域・踵骨傾き・足底圧を確認
- 施術:筋膜リリース、関節モビライゼーション、鍼灸による調整
- 補助具:インソールやテーピングでアライメントを保持
- トレーニング:足底筋群・後脛骨筋・腓骨筋のバランス強化
- 生活指導:靴の選び方、立ち方・歩き方の見直し
当院では、リアライン・コアや足底圧解析などを組み合わせ、正しい足首アライメントの再教育を行っています。

5. まとめ
足首は建物で言う「基礎」。ここが傾けば、膝・骨盤・脊柱などの上位構造も崩れます。
立ち姿や靴底の減り方を一度見直してみましょう。小さなズレが不調の原因になっているかもしれません。
公式SNSアカウント一覧
<<< ブログTOPに戻る
 お知らせ
お知らせ コラム
コラム スタッフブログ
スタッフブログ メディア掲載
メディア掲載
